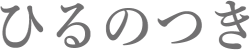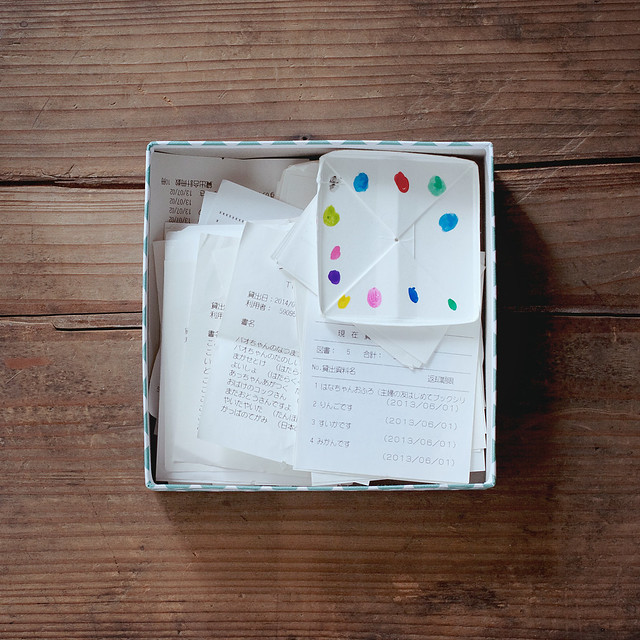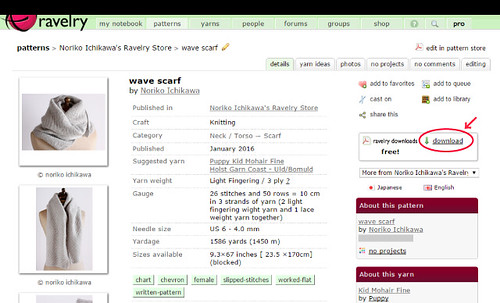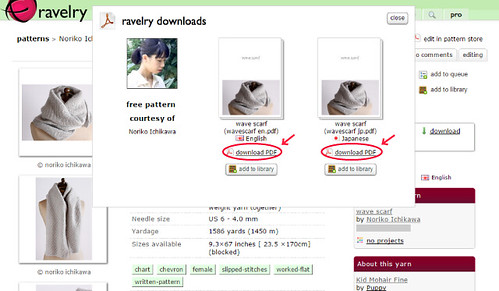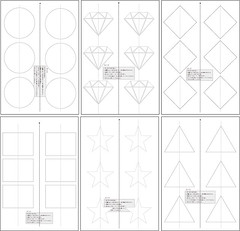一歳を過ぎたころから日に二三度だった娘のお昼寝が、一度にまとまってきました。同時に寝かしつけも延々抱っこから、歌をうたっての添い寝(で、添い乳ナシ)に少しずつ変えていった覚えがあります。
一歳を過ぎたころから日に二三度だった娘のお昼寝が、一度にまとまってきました。同時に寝かしつけも延々抱っこから、歌をうたっての添い寝(で、添い乳ナシ)に少しずつ変えていった覚えがあります。
いわゆる“子守歌大作戦”となったなわけですが、当時のわたしには手持ちの武器(歌える歌)が、それほどありませんでした。
そこで昔ながらの童謡を集めた絵本を探したのですが、残念なことにいい本がなかなか見つかりません。絵が少しばかり甘いアニメ風だったり、歌がずいぶん少なかったり……。ありそうでなかったのですね。
『いっしょにうたって!』『いっぱいうたって!』は、そんなとき偶然知った絵本でした。誰もが知っている、でも歌詞をみないとなかなか歌えない童謡がたっぷり入っていて、真島節子さんの絵も上品でとても愛らしい。避難先の図書館で借りていっぺんで気に入り、すぐに本屋さんで注文しました。
それからほぼ毎日、この二冊には、ほ・ん・と・う・にお世話になりました。
使い過ぎてページはぼろぼろ、テープであちこち補修もしてありますが、道ばたでアリを見つけては歌い、お散歩でこいのぼりを見あげては歌い、寝かしつけ以外にもフル活用。いろいろな思い出が詰まった、文字通り手放せない本になりました。
絵本リスト
どの絵本もこの時期よく読んだものですが、この後も、何度もくり返しず~っと読んでいます(なかには5歳になった今でもときどき読んでいるものも)。なので月齢はあくまで参考程度に。

『いっしょにうたって!』『いっぱいうたって!』(たのしいうたの絵本)
真島節子:絵 こぐま社
「20年前も、いまも、うたわれていて、そして、20年後もうたわれているだろう歌」をそれぞれ29曲づつ収録した歌の絵本。「小さい秋」「くつが鳴る」「あかとんぼ」「春が来た」「汽車ポッポ」「あめふりくまのこ」「こぎつね」などなど、誰もが一度は聞いたこと&歌ったことのある(でも、いざ歌えといわれてもなかなか正確には歌えない)歌の数々が、やさしく朗らかな真島節子さんの絵とともに収められています。子どもと歌いながら日本の豊かな四季を素直に寿げるのもうれしい。簡単な楽譜もついています。
『いっしょにうたって!』
版元の本紹介ページ(収録曲リスト有) / Amazonページ(パソコン) / Amazonページ(モバイル)
『いっぱいうたって!』
版元の本紹介ページ(収録曲リスト有) / Amazonページ(パソコン) / Amazonページ(モバイル)

『おつきさまこっちむいて』(ふしぎなたねシリーズ)
片山令子:文 片山健:絵 福音館書店
ちいさな子はお月さまを見つけるのがほんとうに大好き。大人は慣れてしまって何とも思いませんが、空にあんなものが浮かんでいるなんて(そして光ってるなんて!)、思えばすてきなことですよね。三日月、半月、雲間の月…。どのページにもちゃーんとあるお月さまが、そんな子どもの驚きと喜びをしっかりと充たしてくれるようです。またお月さまを見上げる「ぼく」の横にきまってお父さん、お母さんが描かれているのもうれしい。ほとんどの子どもにとって「お月さまの時間」=夜は、大好きな家族との時間でもありますから。
版元の本紹介ページ
Amazonページ(パソコン) / Amazonページ(モバイル)
『おつきさまこんばんは』
林明子:作 福音館書店
暗い空にお月さまが、少しずつすこしずつのぼってきて…。雲に隠れたお月さまが再び現れ、にっこりとまあるく笑うシーン。娘も一緒になっていつも幸せそうに笑っていました。細部まで磨きあげられた端正な絵、すっと頭に入ってくるやわらかで優しい言葉。上記の『おつきさまこっちむいて』と同じく、初めて「月」というものを知って以来、重度の月マニアになった娘が、とくに気に入っていた名作「お月さま絵本」です。
版元の本紹介ページ
Amazonページ(パソコン) / Amazonページ(モバイル)

『こやぎがめえめえ』(0.1.2えほん)
田島征三:作 福音館書店
「めええ」とないたり、「ぴょん」と跳ねたり、「ぽろぽろ」とうんち(!)をしたり元気いっぱいに遊ぶ、ちいさな「こやぎ」。勢いのある田島さんの筆使いも心地よく、読んでいるとこちらまで開放的な気分になってきます。我が家ではこやぎが転ぶページで、「すってん」と一緒に転ぶマネをするのが“お約束”でした。最後のページが「おっぱいを ちゅう ちゅう」というのも、満足感があっていいのでしょうねえ。
版元の本紹介ページ
Amazonページ(パソコン) / Amazonページ(モバイル)
『だるまさんが』
かがくいひろし:作 ブロンズ新社
ご存知、大人気絵本「だるまさん」シリーズ。娘もやっぱり好きで、「どてっ」では転び、「ぷしゅー」では小さくなり、「ぷっ」ではおならをしたマネをして、全身で堪能していました。一度、ちいさな甥っ子たちに読んであげたときは、それぞれが転んだり、伸びたり、それはもう大騒ぎ。でも最後の「にこっ」で、笑い顔いくつも並んだのには、思わずこちらも「にこっ」。どんな子どもにもヒットするだろう守備範囲の広ーい絵本ゆえ、プレゼントにもおすすめです。
版元の本紹介ページ
Amazonページ(パソコン) / Amazonページ(モバイル)
『たかーいたかい』
いしなべふさこ:作 偕成社
「ぼくのほうが たかいよ」と、椅子に登り、さらには机にあがっていってしまう男の子。なにかに登れば自動的に背が高くなる、という子どもがよくやる「身長のかさ上げ行為」が、かわいらしいイラストでテンポよく描かれています。シンプルな展開ときれいな色あいのせいか、わたしもちいさいころなぜかこの絵本が好きでした。正方形に近いミニ・サイズの厚紙製。
現在、版元品切れ(絶版)のため版元の本紹介ページがなくAmazonにも(今のところ)在庫がないようです